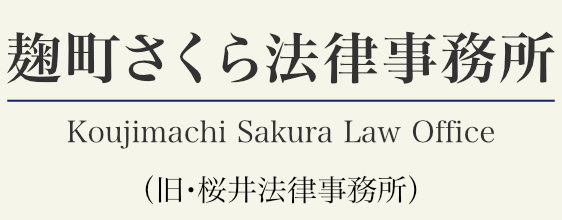麹町さくら法律事務所
【桜井】解説文(2000年以降のもの)
国民生活センター発行のウェブ版「国民生活」に連載中の「保険の基礎知識」。第1回「保険とは」を2014年6月号に掲載。
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11436742/www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-201406_11.pdf
第2次被害における仕組商品の商品特性を踏まえたうえで、そのような商品への「投資」判断に影響を及ぼす重要事項は何であるかを検討したもの。まず、金融商品一般の性質および制度から考え、一般に投資判断に影響を及ぼす重要事項は取引内容、リスク、リターン、コストであることを明らかにし、コストが隠れている金融商品では、隠れたコストの開示がどう扱われているかを整理しました。次に、仕組商品の投資判断に影響を及ぼす重要事項について、日銀の専門家の文献を参考に整理し、構造的理解を背景に隠れたコスト率ないし取引時の時価評価(これらは同じものの表裏の関係にある)を知ることが必要であることを指摘し、さらに、第2次被害における仕組商品では、時価評価はブラックショールズ公式では困難でモンテカルロシミュレーションによっているが、それでもその隠れたコスト率が算出できることを示しました。コスト率は50%前後のものが多いと言われています。最後に、米国では、証券会社を監督するSECが、隠れたコスト総額と発行時の時価評価を目論見書に記載させていることを紹介しました。
第2次被害(2004年~2008年)における仕組商品の商品特性を検討したもの。まず仕組商品を普通型、長期型、倍率型に分けてそれぞれの構造とリスクとリターンの概要を整理しました。次に、仕組商品に共通する商品特性として、大きなコストが隠れていること(リスクに見合う対価を得られないこと)と、そのことに気づきにくいことを指摘しました。最後に、リスクの大きさに気づきにくいという商品特性があることを取り上げ、その理由として、1 商品構造が複雑であるためリスクの所在や大きさがわかりにくくなっていること、2 リスクに見合った対価が得られないため、得られる対価から直感的に想定するリスクは実際より小さなものになること、3 リスクを過小評価する傾向が顕現しやすい商品であるという行動経済学的要因があること、の3つがあることを指摘しました。
ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引業者の広告規制・行為規制、デリバティブ取引・仕組商品規制、デリバティブ取引規制のリフォームについて解説したもの。最後の項目では、証券取引と商品取引を一緒にできる総合取引所構想との関連で、商品先物取引について不招請の勧誘禁止規制を維持すべきことを論じています。
デリバティブ商品の日本上陸の歴史を紹介した後、第1次仕組商品被害(1999年~2000年)の概要とその事件に関する判決を整理し、引続いて第2次仕組商品被害(2004年~2008年)の概要を見たうえ、第1次と第2次の取引態様の違いと商品特性の違いを指摘し、第2次被害においては第1次被害に関する判決と異なる検討の必要性を示唆したもの
ファイナンシャルプランナー向けに、金融商品取引法の取引対象(特に集団投資スキーム持分)、金融商品取引業の概要、最近の改正について解説したもの。第二種金融商品取引業のところでは、MRIインターナショナル事件にも触れています。
2013年7月にオーストラリア・シドニー大学で開催された国際消費者法学会の概要報告。桜井が「日本におけるデリバティブ商品の新しい販売勧誘ルールとその評価」という題で発表した内容と質疑のやりとりを含め、多数の参加者の発表概要をまとめたもの
店頭デリバティブ取引と仕組商品を具体例で比較して、リスクとリターンの実質が同じであることを指摘し、後者についても前者と同レベルの規制をすべきことを提言するもの →PDF(原稿のためレイアウトは異なります)
金融事件の紛争解決機関である金融ADR(証券会社などを対象とするFINMAC,銀行などを対象とする全国銀行協会等)の活動開始後1年半の運用状況を踏まえた、研究者、実務家(弁護士、金融機関法務担当者)6名による座談会
保険のトラブルの実情を踏まえて、平成22年4月施行の保険法の改正点を解説したもの