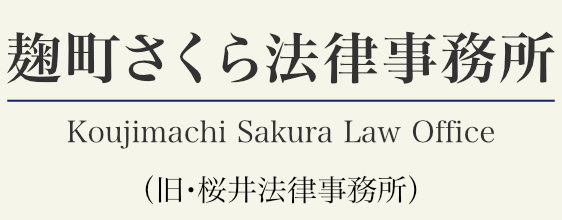活動
麹町さくら法律事務所
活動
弁護士桜井健夫の著書・論文・解説文等
著書(1994年以降のもの)
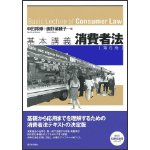
刊行年月:2026年1月
出版社 :日本評論社
大学の「消費者法」講義用テキスト。24名の消費者法等研究者や実務家の共著書で、2013年9月の初版から改訂を重ね第6版となった。今回の第6版から桜井弁護士が加わり、「第15章 金融商品取引と消費者」を担当した。

刊行年月日:2025年8月
出版社 :民事法研究会
単著。支払決済に関する法律の解説書。第1部で支払決済の実際と関連法(銀行法、割賦販売法、資金決済法、電子記録債権法、犯罪収益移転防止法など)を概観し、第2部で支払手段等(預金、デビットカード、デジタルマネー、クレジットカード、電子マネー、コード支払い、収納代行、代引き、キャリア支払い、BNPL、電子記録債権、暗号資産など)別に仕組みと関連法を解説し、第3部でキャッシュレス支払いの消費者問題を検討した。特徴は、1冊で支払決済に関する法律を網羅、キャッシュレス支払いに重点を置き資金決済法2025年改正も織込済、キャッシュレス支払いの消費者問題を検討の3点。https://www.minjiho.com/book/b10140123.html

刊行年月日:2023年2月
出版社 :民事法研究会
単著。金融商品取引法と金融サービス提供法の解説書。特徴は次の3点。
1金融商品や投資に関する前提知識を解説、2消費者の視点を重視、3投資被害救済の法理論を整理
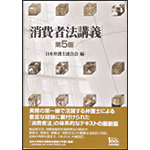
刊行年月:2018年10月
出版社 :日本評論社
法科大学院の「消費者法」講義用テキスト。2004年10月初版から改訂を重ね第5版に。日本弁護士連合会編集で、14名の弁護士による共著。2018年時点の最新の法令や実態を踏まえているので、弁護士の読者も多い。執筆部分「第10章 金融商品と消費者」「第14章 医療サービスと消費者」「コラム 行動経済学と消費者被害」

刊行年月:2018年9月
出版社 :日本評論社
桜井健夫・上柳敏郎・石戸谷豊著。第3版から7年ぶりの全面改訂。金融商品取引法、金融商品販売法のの最新の解説に加えて、民事責任の論点を8つ(被害救済の法理論、投資判断と投機判断、適合性原則、説明義務、フィデューシャリー・デューティーと民事責任、改正民法と金融取引、高齢者と金融取引、銀行の責任)取り上げて解説。最後に、160頁余を割いて200件に及ぶ裁判例を整理して掲載し、民事責任の論点と有機的に結び付けている。
論文等(1998年以降のもの)
2023年12月発行の現代法学45号に論文「説明義務と適合性原則の系譜」を掲載。
https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/11939/1/genhou45-08.pdf
本稿は、証券取引訴訟の重要論点である説明義務と適合性原則について、上柳敏郎弁護士 の足跡など一次資料を中心に生成発展の歴史をまとめるとともに、現在の姿を2023年金商法等改正や仕組債訴訟等に焦点を当てて描いたものである。
第1説明義務の歴史では、ワラント弁護団・全国証券問題研究会と日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の活動から「説明義務違反による不法行為」の判例形成(1996年東京高裁判決など)までたどり(1991年~1997年)、引き続いて、日本版ビッグバン前後における「新しい金融の流れに関する懇談会」、金融審議会第一部会「中間整理(第一次)」、日本弁護士連合会意見書のやりとりを整理した(1997年~1999年)。制度的節目は、この後に来る金融商品販売法の制定(2000年)であり、同法では「説明義務違反による損害賠償責任」を規定した。その法案審議における参考人意見陳述を紹介して、同法では「説明義務違反による不法行為」の判例法理より説明義務の範囲が狭く説明の程度が形式的であることなど問題点を確認し、さらにその後の2006年改正で解消された問題点と残された問題点を切り分けた。そして、それと並行した時期(2001年、2008年)の、信用リスクの説明義務が争点となった判決を2件紹介し、それらが同法制定・改正の影響を間接的に受けながらも、「説明義務違反による不法行為」の理論を深化させていった状況を解説した。
第2説明義務の現在では、まず、「説明義務違反による不法行為」に関する最高裁判決、司法研究報告を紹介した後、2023年金商法等改正法案における説明義務の扱いを解説した。最後に、最近増加している仕組債事件における「説明義務違反による不法行為」について検討した。
第3適合性原則の歴史では、まず同原則が米国の証券取引規制にルーツを持ち、日本では、大蔵省通達「顧客本位の営業姿勢の徹底について」を経て1992年に証券取引法に規定され、平成17年最高裁判決によって、その違反は不法行為となることがあるとして民事責任との架橋がなされて、その判示内容を受けて翌年(2006年)改正の金融商品取引法で、適合性判断の考慮要素として「金融商品取引契約を締結する目的」が追加された経緯を整理した。次に、その翌年(2007年)の東京高裁判決が、適合性原則(顧客適合性)に関する最高裁判決を理解したうえで、過当取引の要件を認定して適合性原則に違反する一任取引であるとして適合性原則を量的適合性に広げたことを指摘し、その後の裁判における量的適合性の定着を示した。その少し後の2010年から2015年にかけて、欧米と日本において、合理的根拠適合性(商品適合性)が適合性原則に含まれる概念として明確になっている。
第4適合性原則の現在では、3段階適用(商品適合性⇒顧客適合性⇒量的適合性)の構造を確認し、販売段階の合理的根拠適合性について、日本証券業協会の自主規制規則等2023年改正の内容を紹介した。最後に、仕組債事件における「適合性原則違反による不法行為」について検討した。
近年普及している「キャッシュレス支払い」の構造・法制度について、消費者の視点から、現実の消費者問題も踏まえて検討した。
https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/11789/1/genhou43-05.pdf
2022年4月8日の日本弁護士連合会消費者問題対策委員会主催シンポジウム「多様化する支払い手段の光と影-キャッシュレス時代の消費者問題」における筆者の報告の基礎となったものに、その後の資金決済法の改正や実態の変化を踏まえて加筆したものである。
まず、キャッシュレス支払いの構造の可視化を試みたうえ、複数の関与者が重層的に関与する場合の問題点を指摘し、組込み型支払いではその問題点の一部が増幅されることを指摘した。次に、資金決済法、銀行法等の2022年改正を踏まえて、支払い法制の消費者法的課題を検討した。最後に、キャッシュレス支払いに関する消費者問題について、7類型に分けて、類型別に被害予防、救済についての方の適用と解釈、立法論を検討した。消費者問題に対し一定の対応が可能な類型もあるが、容易なものは少なく、制度的対応が必要なものが多いことが確認された。
有料老人ホーム入居一時金の一部を初期償却して不返還とする条項(不返還条項、初期償却条項)について検討したもの。
https://repository.tku.ac.jp/dspace/bitstream/11150/11382/1/genhou37-04.pdf
この条項は、制度が変わっても理由を変えて存続してきているものであり、現在は、「想定居住期間を超えて居住継続するリスク」に備える保険的なもの、すなわち、想定居住期間を超過しても新たな賃料は不要となるという対価を得るために、保険料代わりに不返還とすると説明されている。しかし、これは従来から続いている不返還について、新たな理由をこじつけているに過ぎないといえる。
仮に保険的なものであることを前提とすると、この条項は、新種の生存保険と比較して著しく射幸性が高いうえ、不合理、不公正であることを指摘し、消費者契約法10条の問題として検討した。そのうえで、最近の英国の状況を紹介した後、長寿化、有料老人ホームの倒産の増加、新種保険の登場などを踏まえると、日本の有料老人ホーム入居契約においては不返還条項を使用させないことが妥当であると結論付けた。
講演録「投資被害救済の法理論」を『先物・証券取引被害研究第49号』(先物取引被害全国研究会 2019年11月)19頁~35頁に掲載。
2018年9月7日第58回全国証券問題研究会岡山大会での講演をまとめたもの。被害救済の法理論の全体像を確認した後、投資判断と投機判断について詳細に検討し、それを踏まえて、適合性原則について、1意義、2業者ルールと民事ルールの交錯の歴史、3顧客適合性の考慮要素と判断枠組みを考察した。
判例評釈「毎月分配型投資信託の受益証券販売する銀行・投信会社の説明義務」を私法判例リマークス54(2017上)(2017年2月)38頁~41頁に掲載。
https://www.nippyo.co.jp/shop/book/7366.html 東京高裁平成27年1月26日判決につき事案、判旨、先例・学説を紹介し、評論をしたもの。
解説文(2000年以降のもの)
桜井健夫弁護士が、日本弁護士連合会『自由と正義』2025年11月号8頁~17頁に「多様化した支払決済の仕組み・法規制と消費者問題(悪質商法・詐欺助長など)」を掲載
「二弁フロンティア」2025年6月号42頁~53頁に桜井健夫弁護士の講演録「金融商品取引事件の基礎-金サ法・金商法の改正を踏まえて―(後編)」を掲載。
「二弁フロンティア」2025年5月号2頁~11頁に桜井健夫弁護士の講演録「金融商品取引事件の基礎-金サ法・金商法の改正を踏まえて―(前編)」を掲載。
2023年9月15日発行の『現代消費者法№60』(民事法研究会)178頁~184頁に解説文「仕組債被害の救済」を掲載。
『現代消費者法№45』(民事法研究会)105頁~110頁に解説文「決済をめぐる消費者被害」を掲載。
弁護士洞澤美佳の著書・論文・解説文・監修等
著書
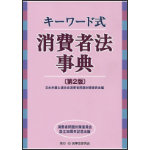
キーワード式消費者法事典第2版(日本弁護士連合会消費者問題対策委員会編著,㈱民事法研究会,2015年)
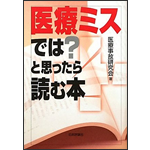
医療ミスでは?と思ったら読む本(医療事故研究会著,㈱日本評論社,2011年)
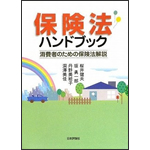
保険法ハンドブック-消費者のための保険法解説(共著,㈱日本評論社,2009年)
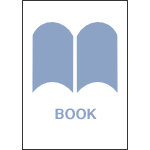
離婚問題法律相談ガイドブック改訂版(東京弁護士会・第一東京弁護士会・第二東京弁護士会編著,2006年)
論文
「生前契約(身元保証サービス)の実情と課題」(共著,現代消費者法32号89頁,2016年9月15日)
解説文・監修等
『Web版国民生活2025年9月号』6頁~9頁 https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202509_02.pdf
東京都DVD「高齢者向け 学んで実践 防ごう! 契約トラブル」(2023年度作成)
「事例で学ぶ消費生活相談の関連法規」連載(ウェブ版「国民生活」,2016年9月から2017年7月まで)
消費者庁「社会への扉 ―12のクイズで学ぶ自立した消費者―(高校生(若年者)向け消費者教育教材 生徒用教材・教師用解説書)」(2017年3月発行)
東京都DVD「リーガル☆レッスン♪〜民法と契約の基礎を学ぶ〜」(2015年度作成)
トピックス
- 2026.01.22
桜井健夫弁護士が共著書『基本講義 消費者法〔第6版〕』(日本評論社)を出版(2026年1月30日)(「第15章 金融商品取引と消費者」を執筆)。https://www.nippyo.co.jp/shop/book/9654.html
- 2025.11.20
2025年10月20日 洞澤美佳弁護士が、東京都消費生活総合センターの令和7年度消費者問題マスター講座で「特定商取引法・割賦販売法の基礎知識」のテーマで講演 https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.lg.jp/manabitai/koza/center/koza_m250624.html
- 2025.11.10
桜井健夫弁護士が、日本弁護士連合会『自由と正義』2025年11月号8頁~17頁に「多様化した支払決済の仕組み・法規制と消費者問題(悪質商法・詐欺助長など)」を掲載
- 2025.10.14
洞澤美佳弁護士が、Web版国民生活2025年9月号6頁~9頁に「シニアのICT利用に関する消費者トラブル」を掲載 https://www.kokusen.go.jp/wko/pdf/wko-202509_02.pdf
- 2025.10.08
2025年10月7日 桜井健夫弁護士が名古屋市にて「キャッシュレス支払関連の法律知識」のテーマで講演(国民生活センター研修 専門講座地域コース愛知県)